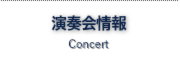演奏曲目徹底分析
ここでは、演奏会で取り上げた曲について独自の視点から分析を試みています。

ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第5番ニ短調作品47
移りゆく「ショスタコーヴィチ」像
ある人物に対するイメージというものは、評者によって様々であろう。同様に歴史上の人物においては、その時代の要請に応じてしばしば変化するという現象が起こる。いや、そればかりか人々の記憶の濃淡すら変化してしまうのである。意外に思うかも知れないが、「革命の英雄」という称号が体制転換によって「反逆者」というレッテルに取って代わられたり、世紀の偉人がもはや過去の人として忘れ去られたりするということは、古今東西の歴史的な変遷からみればごく自然のことであるといえよう。ドミトリ・ショスタコーヴィチ(1906-1975)という人物についてのイメージも例外ではない。だが、20世紀[1]という時代にあって、生前・死後の評価が彼ほど波瀾万丈だった(ことがわかる)人物は、むしろ珍しいといえるのかも知れない。とはいえ、一曲目解説執筆者が作曲家のイメージを勝手に論じるのは、やや越権(えっけん)行為であるともいえる。そこで本稿では、曲目の理解の一助となりかつ屋上屋(おくじょうおく)を架さない範囲で説示・展開するに留めたい。以下作曲家の半生を振り返りつつイメージの変遷を検証することとしたい。
現在のサンクト・ペテルブルグ[2]に生を受けたショスタコーヴィチは、ピアノと作曲を音楽院で学び、19歳で交響曲第1番を発表する。1926年5月12日、ニコライ・マリコ指揮レニングラード・フィルによって初演された。嵐のような大喝采を受け、この作品と作曲者の人気は瞬く間に世界中へと伝播(でんぱ)した。その前衛的作風が有名指揮者からも高い評価を受け、彼は一躍時代の寵児(ちょうじ)となる。しかし、1936年ヨシフ・スターリンによる独裁体制が確固たるものとなると、彼の評価は激変することとなる。
「音楽ならざる荒唐無稽(スンブール)」
1934年に初演されたオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は女主人と使用人との不倫や主人殺しを描き、ソヴィエト国内では2年間で170回以上も上演された。この作品で名声の頂点を極めたショスタコーヴィチだったが、1936年1月28日付の共産党機関紙『プラウダ』紙[3]上で突如攻撃されることとなる。この「プラウダ批判」の影響は甚(はなは)だしく、ショスタコーヴィチの作品は演奏会から姿を消し、ピアニストとしての出演依頼も激減した。時を同じくして、スターリン主導による共産党の権益強化のための粛清(しゅくせい)は党幹部のみならず一般党員や民衆をも含むかたちで進められ、文化・芸術分野においては拡大する共産党の党勢によって統制がエスカレートしていくこととなる。
彼はこの批判に新たな作品で応えようとした。作曲中の交響曲第4番[4]は彼自身がこれまでの自分自身の創作活動の「信条(クレド)(Credo)」と公言し、この曲によって名誉の挽回を画策した。しかし1935年12月11日に予定されていたフィルハーモニーでの初演は行われず[5]、彼への批判はさらに高まるばかりか関係者や親しい友人までもが逮捕・収監・追放・処刑
等の処分を受け、粛清の波は危険水域に迫ろうとしていた。この粛清を免れるには、イデオロギー的に更正した事を証明する作品を発表することが求められたと思われる。
交響曲第5番
1937年4月に作曲が始められた交響曲第5番は、わずか3ヶ月で完成されたとされている。10月に作曲家同盟での予備審査を経たあと、11月21日にエフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団での初演が決定された。そして、初演は大成功のうちに終わったのである。
交響曲第5番では、これまでの前衛的な作風は陰をひそめ、4楽章形式かつ一部を除いて標準的なオーケストラ編成という古典的な手法によって作られている。巧みなリズム・和音の構成によって苦悩から歓喜への発展モデルを示し、人々が帝政ロシア時代の圧政から社会主義革命によって救われるという大作が生み出された瞬間であった。
初演後、ソ連作家同盟議長のアレクセイ・N・トルストイ(1883-1945)[6]が『イズヴェスチヤ』紙に「ショスタコーヴィチの交響曲第5番」と題した論文を掲載し、交響曲全体の流れを精神的危機の克服によって革命的理想に目覚めていく主人公を成長過程と捉え発表した。ほどなくして、ショスタコーヴィチ自身も私の『創造的回答』と題された論文でトルストイを引用し、「主人公」の葛藤と人生を肯定する楽観的なフィナーレがプラウダ批判後の自身の精神的危機を反映していることを認めた。このような一連の解釈の積み重ねによって、ショスタコーヴィチの「ペレストロイカ(人格改造)」は既成事実化したのである。交響曲第5番で名誉挽回を果たしたショスタコーヴィチは、矢継ぎ早に新作を発表し続け、さらなる躍進を遂げるのであった。
彼以外にも、粛清期を生きながらえた芸術家にとって、大戦期とりわけ独ソ戦争時は大いに創作意欲をかきたてられた時期であった。スターリン自身も国内での弾圧政策を一時棚上げし、批判された芸術家達の地位を回復させてまで彼らを大政翼賛的プロパガンダに利用した。戦争への煽動(せんどう)によるもであったにせよ、ある程度の自由が認められたことで失われた以前の輝きを取り戻したのである。ショスタコーヴィチ自身も創作活動の傍ら、人民義勇軍に志願するなど精力的に活動(実際には義勇軍には入隊できず音楽院消防隊へ入隊)し、全世界へ彼が鉄兜(かぶと)を被った映像が流された。こうして、ショスタコーヴィチには「共産党の御用音楽家」というイメージが確定するのであった。
その後、晩年にも精力的に作品を発表し続けたが、1975年ついに波乱に満ちた生涯を閉じたのである。ソ連共産党機関紙『プラウダ』には追悼記事が掲載され、模範的芸術家であったことを実証する数々の役職・称号・表彰歴等が列挙されたのである。
「ショスタコーヴィチ」像の転換
だが、彼の死後の展開は、複雑な色彩を帯びることとなる。生前から、「20世紀の作曲家」としてのショスタコーヴィチの評価は、少なくとも社会主義圏外では凋落(ちょうらく)の一途を辿(たど)っていた。大戦後、前衛音楽の圧倒的な展開を経験した西側諸国の音楽家にとって、度重なる党からの批判を受けて交響曲や弦楽四重奏曲など前世紀的なジャンルで調性音楽を書き続けたショスタコーヴィチは、芸術的な妥協を重ねた政治的な日和見(ひよりみ)主義者・大衆迎合的で退嬰(たいえい)的な作曲家の典型とされていた。
こうした中、1979年にアメリカで翻訳・出版されたソロモン・ヴォルコフ『証言—ショスタコーヴィチの回想録—』によって、ショスタコーヴィチの新たな一面がクローズ・アップされることとなる[7]。この著作の登場後、ショスタコーヴィチ自身の生涯にわたる共産主義への根深い嫌悪(けんお)や作品に込められた反体制メッセージが明るみに出た。スターリン体制下での知識人への弾圧を赤裸々に暴露(ばくろ)したこの著作の登場によって、ショスタコーヴィチの評価は大きく転換することとなる。それまで、ショスタコーヴィチに貼られていた恭順(きょうじゅん)の身振りを示す「共産党の忠実な息子」というレッテルは、「社会主義の殉教者」に取って代わり、本人が吐露(とろ)した「私の交響曲はすべて墓碑銘である」といった表現は、「張りめぐらされた蜘蛛の巣」や「強制された歓喜」といったフレーズとともにアカデミズムの範疇(はんちゅう)を超え、ライナー・ノーツや演奏会解説等を賑わし、広く人口に膾炙(かいしゃ)することとなった。
これにより、体制擁護の語法に秘められたアイロニックな体制批判とショスタコーヴィチの内なる葛藤が白日の下にさらされ、ショスタコーヴィチ像と諸作品の解釈は複雑でアンビヴァレントなものとなっていくこととなる。
ヴォルコフ真贋(しんがん)論争
かくしてショスタコーヴィチの作品は西側市場でも再評価され、様々な形で取り上げられた。その後研究も進み、作品中には種々のアイロニカルな引用が認められることとなる。
一見大衆迎合的な姿勢を見せてきた彼のイメージは、「反体制」の信条をひた隠しにした抑圧への抵抗と解釈されることとなった。だがこの動きに対し、アメリカの音楽学者ローレル・E・ファーイが疑義を申したてたのである。彼は『ショスタコーヴィチ対ヴォルコフ−誰の“証言”か?』を発表し、ヴォルコフの『証言』はショスタコーヴィチ自身の言葉ではないという主張を行った[8]。ヴォルコフが取材によって得たショスタコーヴィチ本人の口述による原稿も取材回数・時間等の調査で信憑性に疑義が向けられたのである。
ファーイはその後も悉皆(しっかい)調査を進め、以前は閲覧不可能だった『証言』のロシア語タイプ原稿のフォト・コピーを詳細に分析し、さらなる証拠を明示した上で『ヴォルコフの“証言”再考』を発表、ショスタコーヴィチが署名した部分は他の論文からの切り貼り等で偽装されたものであると断言した。これにより、真贋論争には終止符が打たれることとなった。
だが、その後も多くの音楽学者・批評家・ジャーナリスト達は、典拠として『証言』を引用し続ける事となる。『証言』は、「ソ連共産党の御用達作曲家」というイメージを払拭(ふっしょく)し、西側の音楽市場がショスタコーヴィチの作品を受容する上で好都合な解釈を創り出すことに成功している[9]。そればかりでなく、ファーイ自身も『証言』の内容に対しては決して鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問うのではなく、「1979年以前に発表されたどの資料よりも生前のショスタコーヴィチの個人的見解を忠実に再現している」と述べている[10]。
真贋論争を経たショスタコーヴィチ像は文字通り換骨奪胎(かんこつだったい)し、「体制擁護」や「反体制」といった単一な論理を止揚(しよう)するものとなった。ともすればこれらのイメージは、今日的あるいは後世の学問的な理解に基づく「創られた」イメージとの批判もあろう。だが厳戒統制下にあった当時の言説が必ずしも真実を語っているとは言えないという状況であることに鑑みれば、このような事後的なアプローチもまた価値を生むはずである。現時点で我々は、今後のイメージの移り変わりが帰趨(きすう)するところを知らない。だが「ショスタコーヴィチ」像は、その複雑な魅力をもつ諸作品とともに「歴史の厚み」が付け加えられ、連綿と語り継がれていくに違いない。とりわけ重要なメルクマールとなる交響曲第5番は、我々にとって最も資するところが大きい作品のひとつであり、この作品を取り上げて演奏する価値は大きい。このような視座に基づけば、我々もまた後塵(こうじん)を拝することなく思索を深化・展開させることで理解を深め、後代へこの高大な交響曲を伝達していくという責務を負うこととなろう。
第1楽章:モデラート−アレグロ・ノン・トロッポ
低弦と高弦のオクターヴでのカノンによって開始する。跳躍と導音進行とを交互に繰り返し展開する。突如として行進曲風のフレーズが登場し、やがて速度を増していく。暴力的なまで激しさを増すと最後はシロフォンを加えて、高弦のかなりの技巧を要する再現部に突入してゆく。コーダはチェレスタの半音階を伴いながら、ピアニッシモによって消え入る。
第2楽章:アレグレット
伝統的なスケルツォであり、低音弦の主題から始まる。その後、行進曲風だが2拍子ではなく3拍子のホルンの楽句を伴い進行していく。独奏ヴァイオリンのソロにも注目されたい。
第3楽章:ラルゴ
ホルンを含む全ての金管を外し、3群のヴァイオリンと2群のヴィオラとチェロ、1群のコントラバスと細分化している。ロシア正教における死者への祈りである「パニヒダ」の旋律を用いたこの楽章では、永眠者の魂への安息と永遠の命が与えられる希望を表したものである。初演では、演奏中に男女を問わず非常に多くの聴衆が涙を流し、党幹部はそれをロシア革命の犠牲者への祈りだと解釈した。しかし『証言』では、スターリンのよる粛清の犠牲者に対する祈りだとの記載があり、ショスタコーヴィチの秘められたメッセージを読み取ることができよう。
第4楽章:アレグロ・ノン・トロッポ
光彩陸離たる行進曲風のフィナーレではトランペットとトロンボーンのオクターヴで始まる冒頭の旋律は、ビゼーの歌劇『カルメン』のハバネラからの借用であるとされ、『カルメン』にあるフランス語の「Prends garde à toi!(プラン・ガルダ・トワ)」(「気をつけろ!」)[11]のニ長調「嬰へ音」(「ラ・レ・ミ・ファ♯」のファ♯の部分)を半音下げた「へ音」に変更してニ短調化(「ラ・レ・ミ・ファ」)したものであると解釈されている。この「気をつけろ!」を変形して挿入することにより、スターリン体制の進展への危惧と批判を込めた歌詞を内包しているとされている。
また、終結部に向かい延々と続く252回のA音の連打は、Aを「la」(古ロシア語で「私」を意味している音)として用いていることから、ショスタコーヴィチの内なる声を表現しているという解釈もある[12]。最後は主音二音のユニゾンによって、苦悩から歓喜に至る大勝利を表現し曲を閉じる。だがここでは、先ほどの短調化したフレーズがニ長調としてはっきり登場する。初演においては、聴衆の多くが1人また1人と立ち上がりはじめ、曲が終わると雷鳴のような拍手が白いフィルハーモニー・ホールの柱を揺り動かしたという[13]。
註
現在のサンクト・ペテルブルグ[2]に生を受けたショスタコーヴィチは、ピアノと作曲を音楽院で学び、19歳で交響曲第1番を発表する。1926年5月12日、ニコライ・マリコ指揮レニングラード・フィルによって初演された。嵐のような大喝采を受け、この作品と作曲者の人気は瞬く間に世界中へと伝播(でんぱ)した。その前衛的作風が有名指揮者からも高い評価を受け、彼は一躍時代の寵児(ちょうじ)となる。しかし、1936年ヨシフ・スターリンによる独裁体制が確固たるものとなると、彼の評価は激変することとなる。
「音楽ならざる荒唐無稽(スンブール)」
1934年に初演されたオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は女主人と使用人との不倫や主人殺しを描き、ソヴィエト国内では2年間で170回以上も上演された。この作品で名声の頂点を極めたショスタコーヴィチだったが、1936年1月28日付の共産党機関紙『プラウダ』紙[3]上で突如攻撃されることとなる。この「プラウダ批判」の影響は甚(はなは)だしく、ショスタコーヴィチの作品は演奏会から姿を消し、ピアニストとしての出演依頼も激減した。時を同じくして、スターリン主導による共産党の権益強化のための粛清(しゅくせい)は党幹部のみならず一般党員や民衆をも含むかたちで進められ、文化・芸術分野においては拡大する共産党の党勢によって統制がエスカレートしていくこととなる。
彼はこの批判に新たな作品で応えようとした。作曲中の交響曲第4番[4]は彼自身がこれまでの自分自身の創作活動の「信条(クレド)(Credo)」と公言し、この曲によって名誉の挽回を画策した。しかし1935年12月11日に予定されていたフィルハーモニーでの初演は行われず[5]、彼への批判はさらに高まるばかりか関係者や親しい友人までもが逮捕・収監・追放・処刑
等の処分を受け、粛清の波は危険水域に迫ろうとしていた。この粛清を免れるには、イデオロギー的に更正した事を証明する作品を発表することが求められたと思われる。
交響曲第5番
1937年4月に作曲が始められた交響曲第5番は、わずか3ヶ月で完成されたとされている。10月に作曲家同盟での予備審査を経たあと、11月21日にエフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団での初演が決定された。そして、初演は大成功のうちに終わったのである。
交響曲第5番では、これまでの前衛的な作風は陰をひそめ、4楽章形式かつ一部を除いて標準的なオーケストラ編成という古典的な手法によって作られている。巧みなリズム・和音の構成によって苦悩から歓喜への発展モデルを示し、人々が帝政ロシア時代の圧政から社会主義革命によって救われるという大作が生み出された瞬間であった。
初演後、ソ連作家同盟議長のアレクセイ・N・トルストイ(1883-1945)[6]が『イズヴェスチヤ』紙に「ショスタコーヴィチの交響曲第5番」と題した論文を掲載し、交響曲全体の流れを精神的危機の克服によって革命的理想に目覚めていく主人公を成長過程と捉え発表した。ほどなくして、ショスタコーヴィチ自身も私の『創造的回答』と題された論文でトルストイを引用し、「主人公」の葛藤と人生を肯定する楽観的なフィナーレがプラウダ批判後の自身の精神的危機を反映していることを認めた。このような一連の解釈の積み重ねによって、ショスタコーヴィチの「ペレストロイカ(人格改造)」は既成事実化したのである。交響曲第5番で名誉挽回を果たしたショスタコーヴィチは、矢継ぎ早に新作を発表し続け、さらなる躍進を遂げるのであった。
彼以外にも、粛清期を生きながらえた芸術家にとって、大戦期とりわけ独ソ戦争時は大いに創作意欲をかきたてられた時期であった。スターリン自身も国内での弾圧政策を一時棚上げし、批判された芸術家達の地位を回復させてまで彼らを大政翼賛的プロパガンダに利用した。戦争への煽動(せんどう)によるもであったにせよ、ある程度の自由が認められたことで失われた以前の輝きを取り戻したのである。ショスタコーヴィチ自身も創作活動の傍ら、人民義勇軍に志願するなど精力的に活動(実際には義勇軍には入隊できず音楽院消防隊へ入隊)し、全世界へ彼が鉄兜(かぶと)を被った映像が流された。こうして、ショスタコーヴィチには「共産党の御用音楽家」というイメージが確定するのであった。
その後、晩年にも精力的に作品を発表し続けたが、1975年ついに波乱に満ちた生涯を閉じたのである。ソ連共産党機関紙『プラウダ』には追悼記事が掲載され、模範的芸術家であったことを実証する数々の役職・称号・表彰歴等が列挙されたのである。
「ショスタコーヴィチ」像の転換
だが、彼の死後の展開は、複雑な色彩を帯びることとなる。生前から、「20世紀の作曲家」としてのショスタコーヴィチの評価は、少なくとも社会主義圏外では凋落(ちょうらく)の一途を辿(たど)っていた。大戦後、前衛音楽の圧倒的な展開を経験した西側諸国の音楽家にとって、度重なる党からの批判を受けて交響曲や弦楽四重奏曲など前世紀的なジャンルで調性音楽を書き続けたショスタコーヴィチは、芸術的な妥協を重ねた政治的な日和見(ひよりみ)主義者・大衆迎合的で退嬰(たいえい)的な作曲家の典型とされていた。
こうした中、1979年にアメリカで翻訳・出版されたソロモン・ヴォルコフ『証言—ショスタコーヴィチの回想録—』によって、ショスタコーヴィチの新たな一面がクローズ・アップされることとなる[7]。この著作の登場後、ショスタコーヴィチ自身の生涯にわたる共産主義への根深い嫌悪(けんお)や作品に込められた反体制メッセージが明るみに出た。スターリン体制下での知識人への弾圧を赤裸々に暴露(ばくろ)したこの著作の登場によって、ショスタコーヴィチの評価は大きく転換することとなる。それまで、ショスタコーヴィチに貼られていた恭順(きょうじゅん)の身振りを示す「共産党の忠実な息子」というレッテルは、「社会主義の殉教者」に取って代わり、本人が吐露(とろ)した「私の交響曲はすべて墓碑銘である」といった表現は、「張りめぐらされた蜘蛛の巣」や「強制された歓喜」といったフレーズとともにアカデミズムの範疇(はんちゅう)を超え、ライナー・ノーツや演奏会解説等を賑わし、広く人口に膾炙(かいしゃ)することとなった。
これにより、体制擁護の語法に秘められたアイロニックな体制批判とショスタコーヴィチの内なる葛藤が白日の下にさらされ、ショスタコーヴィチ像と諸作品の解釈は複雑でアンビヴァレントなものとなっていくこととなる。
ヴォルコフ真贋(しんがん)論争
かくしてショスタコーヴィチの作品は西側市場でも再評価され、様々な形で取り上げられた。その後研究も進み、作品中には種々のアイロニカルな引用が認められることとなる。
一見大衆迎合的な姿勢を見せてきた彼のイメージは、「反体制」の信条をひた隠しにした抑圧への抵抗と解釈されることとなった。だがこの動きに対し、アメリカの音楽学者ローレル・E・ファーイが疑義を申したてたのである。彼は『ショスタコーヴィチ対ヴォルコフ−誰の“証言”か?』を発表し、ヴォルコフの『証言』はショスタコーヴィチ自身の言葉ではないという主張を行った[8]。ヴォルコフが取材によって得たショスタコーヴィチ本人の口述による原稿も取材回数・時間等の調査で信憑性に疑義が向けられたのである。
ファーイはその後も悉皆(しっかい)調査を進め、以前は閲覧不可能だった『証言』のロシア語タイプ原稿のフォト・コピーを詳細に分析し、さらなる証拠を明示した上で『ヴォルコフの“証言”再考』を発表、ショスタコーヴィチが署名した部分は他の論文からの切り貼り等で偽装されたものであると断言した。これにより、真贋論争には終止符が打たれることとなった。
だが、その後も多くの音楽学者・批評家・ジャーナリスト達は、典拠として『証言』を引用し続ける事となる。『証言』は、「ソ連共産党の御用達作曲家」というイメージを払拭(ふっしょく)し、西側の音楽市場がショスタコーヴィチの作品を受容する上で好都合な解釈を創り出すことに成功している[9]。そればかりでなく、ファーイ自身も『証言』の内容に対しては決して鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問うのではなく、「1979年以前に発表されたどの資料よりも生前のショスタコーヴィチの個人的見解を忠実に再現している」と述べている[10]。
真贋論争を経たショスタコーヴィチ像は文字通り換骨奪胎(かんこつだったい)し、「体制擁護」や「反体制」といった単一な論理を止揚(しよう)するものとなった。ともすればこれらのイメージは、今日的あるいは後世の学問的な理解に基づく「創られた」イメージとの批判もあろう。だが厳戒統制下にあった当時の言説が必ずしも真実を語っているとは言えないという状況であることに鑑みれば、このような事後的なアプローチもまた価値を生むはずである。現時点で我々は、今後のイメージの移り変わりが帰趨(きすう)するところを知らない。だが「ショスタコーヴィチ」像は、その複雑な魅力をもつ諸作品とともに「歴史の厚み」が付け加えられ、連綿と語り継がれていくに違いない。とりわけ重要なメルクマールとなる交響曲第5番は、我々にとって最も資するところが大きい作品のひとつであり、この作品を取り上げて演奏する価値は大きい。このような視座に基づけば、我々もまた後塵(こうじん)を拝することなく思索を深化・展開させることで理解を深め、後代へこの高大な交響曲を伝達していくという責務を負うこととなろう。
第1楽章:モデラート−アレグロ・ノン・トロッポ
低弦と高弦のオクターヴでのカノンによって開始する。跳躍と導音進行とを交互に繰り返し展開する。突如として行進曲風のフレーズが登場し、やがて速度を増していく。暴力的なまで激しさを増すと最後はシロフォンを加えて、高弦のかなりの技巧を要する再現部に突入してゆく。コーダはチェレスタの半音階を伴いながら、ピアニッシモによって消え入る。
第2楽章:アレグレット
伝統的なスケルツォであり、低音弦の主題から始まる。その後、行進曲風だが2拍子ではなく3拍子のホルンの楽句を伴い進行していく。独奏ヴァイオリンのソロにも注目されたい。
第3楽章:ラルゴ
ホルンを含む全ての金管を外し、3群のヴァイオリンと2群のヴィオラとチェロ、1群のコントラバスと細分化している。ロシア正教における死者への祈りである「パニヒダ」の旋律を用いたこの楽章では、永眠者の魂への安息と永遠の命が与えられる希望を表したものである。初演では、演奏中に男女を問わず非常に多くの聴衆が涙を流し、党幹部はそれをロシア革命の犠牲者への祈りだと解釈した。しかし『証言』では、スターリンのよる粛清の犠牲者に対する祈りだとの記載があり、ショスタコーヴィチの秘められたメッセージを読み取ることができよう。
第4楽章:アレグロ・ノン・トロッポ
光彩陸離たる行進曲風のフィナーレではトランペットとトロンボーンのオクターヴで始まる冒頭の旋律は、ビゼーの歌劇『カルメン』のハバネラからの借用であるとされ、『カルメン』にあるフランス語の「Prends garde à toi!(プラン・ガルダ・トワ)」(「気をつけろ!」)[11]のニ長調「嬰へ音」(「ラ・レ・ミ・ファ♯」のファ♯の部分)を半音下げた「へ音」に変更してニ短調化(「ラ・レ・ミ・ファ」)したものであると解釈されている。この「気をつけろ!」を変形して挿入することにより、スターリン体制の進展への危惧と批判を込めた歌詞を内包しているとされている。
また、終結部に向かい延々と続く252回のA音の連打は、Aを「la」(古ロシア語で「私」を意味している音)として用いていることから、ショスタコーヴィチの内なる声を表現しているという解釈もある[12]。最後は主音二音のユニゾンによって、苦悩から歓喜に至る大勝利を表現し曲を閉じる。だがここでは、先ほどの短調化したフレーズがニ長調としてはっきり登場する。初演においては、聴衆の多くが1人また1人と立ち上がりはじめ、曲が終わると雷鳴のような拍手が白いフィルハーモニー・ホールの柱を揺り動かしたという[13]。
註
[1] 本来は100年を単位とした時間区分であるが、厳密にいえばショスタコーヴィチの生きた時代とは合致しない。ここでは、1789年のフランス革命から1914年の第一次世界大戦までを「長い19世紀」とし、1914年からソ連が崩壊し米ソ冷戦体制が終結した1991年を「短い20世紀」とするホブズボームの用語に依拠している。エリック・ホブズボーム(河合秀和訳)『20世紀の歴史—極端な時代—〈上〉〈下〉』(三省堂、1996年)。
[2]1914年、第一次世界大戦が始まりロシアがドイツと交戦状態に入ると、ロシア語風にペトログラード (Петроград)と改められた。さらにロシア革命によりソヴィエト連邦が成立すると、1924年よりレーニンにちなんでレニングラード (Ленинград) と改称された。しかし、ソ連崩壊後の1991年に住民投票によってロシア帝国時代のサンクト・ペテルブルグに戻った。
[3] ソ連共産党中央委員会機関紙へ無署名で投稿された。この論文は、その他の新聞や各分野の専門誌ではなく中央委員会機関紙に投稿されたことで、党執行部、とりわけスターリンの意見であるとほのめかされた。千葉潤『ショスタコーヴィチ 作曲家・人と作品シリーズ』(音楽之友社、2005年)、66-68頁。
[4]当初、フリッツ・シュティードリーとオットー・クレンペラーという著名な指揮者2人がこの交響曲に関心を示しており、それぞれ自分の指揮する演奏会で取り上げる約束をしていた。千葉、前掲書、75-76頁。
[5]交響曲第4番の撤回理由については様々な説が存在する。レニングラード・フィルハーモニーでの初演を予定していたシュティードリーは音楽を理解できておらず、悪印象を恐れて撤回したとする説(のちにショスタコーヴィチやコンドラシンよって流布された)。リハーサル中に楽団員から曲への疑義が呈され、紛糾を恐れて楽譜を回収したとする説(シュティードリーの回想による)。作曲家同盟の幹部が突如リハーサルに訪れ、自発的な作品の撤回を促したとする説(グリークマンの回想による)。千葉、前掲書、75-76頁。
[6] 『おおきなかぶ』などに代表される小説家、SF作家。
[7] Solomon Volkov, ed. (trans. Antonina W. Bouis), Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich (New York, NY; Harper & Row, 1979) [ソロモン・ヴォルコフ編(水野忠夫訳)『ショスタコーヴィチの証言』(中央公論新社、1980、2001年)].
[8] Laurel E Fay, Shostakovich: A Life New Edition (New York, NY; Oxford University Press, 2005, originally published in 2000)[ローレル・E・ファーイ(藤岡啓介・佐々木千恵訳)『ショスタコーヴィチ ある生涯 [改訂新版]』(アルファベータ、2005年)] .
[9] Francis Maes (Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans trans.), A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar (Berkeley, CA; University of California Press, 2002), p. 347.
[11] “prendre(動)”に“garde(名)”を伴う。“prendre garde”で「気をつける」の意味となり、命令形、対象の前置詞“à”二人称代名詞の強制形“toi”を用いて「気をつけろ!」の訳となる。『カルメン』では、カルメンが「ハバネラ」を歌い甘美な言葉で誘惑するシーンで合唱が呼応する部分の歌詞であり、ショスタコーヴィチが半音下げて借用したため体制批判のメタ・メッセージが込められているという解釈が成り立つ。「NHKクラシックミステリー名曲探偵アマデウス」制作チーム編『NHKクラシックミステリー 名曲探偵アマデウス』(ナツメ社、2010年)、148頁。
[12] 「NHKクラシックミステリー名曲探偵アマデウス」制作チーム、前掲書、148頁。
参考文献
Theodor Adorno “Zum Problem der Reproduktion,” in Gesammelte Schriften 19 (Frankfult, Suhrkamp, 1984).
Laurel E Fay, Shostakovich: A Life New Edition (New York, NY; Oxford University Press, 2005, originally published in 2000)[ローレル・E・ファーイ(藤岡啓介・佐々木千恵訳)『ショスタコーヴィチ ある生涯 [改訂新版]』(アルファベータ、2005年)] .
Jacques Lacan, Écrits 1 (Paris; Seuil, 1966)[ジャック・ラカン(宮本忠雄・竹内迪也・高橋徹・佐々木孝次訳)『エクリⅠ』(弘文堂、1972年)].
Emmanuel Lévinas et François Poirié, Qui êtes-vous, Emmanuel Lévinas?, (La Manufacture, 1987).
Francis Maes (trans. Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans), A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar (Berkeley, CA; University of California Press, 2002).
Solomon Volkov, ed. (trans. Antonina W. Bouis), Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich (New York, NY; Harper & Row, 1979) [ソロモン・ヴォルコフ編(水野忠夫訳)『ショスタコーヴィチの証言』(中央公論新社、1980、2001年)].
Theodor Adorno “Zum Problem der Reproduktion,” in Gesammelte Schriften 19 (Frankfult, Suhrkamp, 1984).
Laurel E Fay, Shostakovich: A Life New Edition (New York, NY; Oxford University Press, 2005, originally published in 2000)[ローレル・E・ファーイ(藤岡啓介・佐々木千恵訳)『ショスタコーヴィチ ある生涯 [改訂新版]』(アルファベータ、2005年)] .
Jacques Lacan, Écrits 1 (Paris; Seuil, 1966)[ジャック・ラカン(宮本忠雄・竹内迪也・高橋徹・佐々木孝次訳)『エクリⅠ』(弘文堂、1972年)].
Emmanuel Lévinas et François Poirié, Qui êtes-vous, Emmanuel Lévinas?, (La Manufacture, 1987).
Francis Maes (trans. Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans), A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar (Berkeley, CA; University of California Press, 2002).
Solomon Volkov, ed. (trans. Antonina W. Bouis), Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich (New York, NY; Harper & Row, 1979) [ソロモン・ヴォルコフ編(水野忠夫訳)『ショスタコーヴィチの証言』(中央公論新社、1980、2001年)].
Robert Conquest, The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties (New York, NY; Macmillan, 1968, revised ed., 1971)[ロバート・コンクエスト(片山さとし訳)『スターリンの恐怖政治(上・下)』(三一書房、1976年)].
Elizabeth Wilson, Shostakovich: A Life Remembered (Princeton, NJ; Princeton University Press, 1994).
「NHKクラシックミステリー名曲探偵アマデウス」制作チーム編『NHKクラシックミステリー 名曲探偵アマデウス』(ナツメ社、2010年)
岡田暁生『音楽の聴き方』(中央公論新社、2009年)
音楽之友社編『作曲家別名曲解説ライブラリー:ショスタコーヴィチ』(音楽之友社、1993年)
千葉潤『ショスタコーヴィチ 作曲家・人と作品シリーズ』(音楽之友社、2005年)
若尾祐司・和田光弘編 『歴史の場―史跡・記念碑・記憶—』(名古屋大学出版会、2010年)
「NHKクラシックミステリー名曲探偵アマデウス」制作チーム編『NHKクラシックミステリー 名曲探偵アマデウス』(ナツメ社、2010年)
岡田暁生『音楽の聴き方』(中央公論新社、2009年)
音楽之友社編『作曲家別名曲解説ライブラリー:ショスタコーヴィチ』(音楽之友社、1993年)
千葉潤『ショスタコーヴィチ 作曲家・人と作品シリーズ』(音楽之友社、2005年)
若尾祐司・和田光弘編 『歴史の場―史跡・記念碑・記憶—』(名古屋大学出版会、2010年)
ジョルジュ・ビゼー歌劇《カルメン》第1組曲・第2組曲
フリッツ・ホフマン編曲版
ジョルジュ・ビゼー(1838−1875)は、声楽教師の父アドルフ・アマンとピアニストの母エメ・マリ・ルイーズ・レオポルディーヌ・ジョゼフィーヌの間にパリで生を受け、早くから音楽的才能を発揮したと言われている。10歳になる直前の1848年10月9日付でパリ音楽院に正式に入学している。
音楽院ではジンメルマンとグノーから対位法とフーガを学び、その後移ったフロマンタル・アレヴィのクラスでも順調に学業を修めた。1855年には交響曲ハ長調を作曲しており、グノーがピアノ4手編曲した版も存在している[1]。に作曲家の登竜門であるローマ大賞に二度応募し、1857年に第1位と奨学金[2]を得てローマへ旅立っている。このとき彼は、大御所ロッシーニの紹介状を手にしていたとされている。
しかし、2年間の留学も終盤にさしかかる頃、母の容態が芳しくないという知らせを受ける。ビゼーはすぐさまパリに戻り、1861年9月に母が没するまで看病を行った。当時彼は、作曲家としての将来に疑問を抱いており、ピアニストとしての活動に傾倒していたが、それも私的な集まりや慈善演奏会などに留まっていたといわれている。時期を同じくして、
師のアレヴィがリストに彼を紹介している。ビゼーはこのとき、リストが持参した自筆譜を初見でほぼ完璧に演奏したという。そんな中作曲活動も再開していくこととなる。《大守のグズラ》、《イワン四世》、《真珠とり》などを立て続けに作曲したが、演奏されなかったり公演が芳しくなかったりなど、不遇の時代が続く。そんな中、師アレヴィが病気でこの世を去り、大きな後ろ盾のひとつを失ってしまった。だが、状況は好転する。彼の交響曲「ローマ」が初演され好評を博し、アレヴィの娘、ジュヌヴィエーヴと結婚した[3]。
19世紀パリの音楽と社会
ビゼーの生きた19世紀のフランスは、まさしく激動の時代であった。フランス革命以後の相次ぐ政変[4]、2度のパリ万博(1855・1867年)、ジョルジュ・オスマンによるパリの大改造など、人々の生活や価値観が一変したと思われる歴史的なトピックは枚挙に暇(いとま)がない。それは政体の変化もさることながら、公教育政策などを通じて「フランス」という国家が創り上げられていった時期でもある[5]。
この時代は、音楽というジャンルにおいても大きな変貌を遂げた時期であるといえる。アンシャン・レジーム期には王侯貴族の私的な消費物であった音楽は、名望家・ブルジョア(中産階級)の台頭によって主たる消費者が大衆化していくこととなる。音楽は見世物としての進化・深化を遂げ、サロンやコンサートホールではリストやショパンといったヴィルトゥオーゾ(名手)の園雄に熱狂的な観客が押し寄せた。またパリには次々とオペラ劇場が建設され、まさしく市民革命的熱気ともいうべきオペラ熱によって人々は(着飾って)劇場を訪れ観劇していった。この劇場の壮大な舞台装置を前提としてグランド・オペラと呼ばれるジャンルが確立する。こうした劇場に通うことが、(貴族ではない)上流階級の最大の箔のひとつであったといえる[6]。音楽家にとっては、一大マーケットであるパリで成果を挙げることが求められ、オペラでの成功が音楽家としての成功であったといえる。
《カルメン》の初演
音楽院ではジンメルマンとグノーから対位法とフーガを学び、その後移ったフロマンタル・アレヴィのクラスでも順調に学業を修めた。1855年には交響曲ハ長調を作曲しており、グノーがピアノ4手編曲した版も存在している[1]。に作曲家の登竜門であるローマ大賞に二度応募し、1857年に第1位と奨学金[2]を得てローマへ旅立っている。このとき彼は、大御所ロッシーニの紹介状を手にしていたとされている。
しかし、2年間の留学も終盤にさしかかる頃、母の容態が芳しくないという知らせを受ける。ビゼーはすぐさまパリに戻り、1861年9月に母が没するまで看病を行った。当時彼は、作曲家としての将来に疑問を抱いており、ピアニストとしての活動に傾倒していたが、それも私的な集まりや慈善演奏会などに留まっていたといわれている。時期を同じくして、
師のアレヴィがリストに彼を紹介している。ビゼーはこのとき、リストが持参した自筆譜を初見でほぼ完璧に演奏したという。そんな中作曲活動も再開していくこととなる。《大守のグズラ》、《イワン四世》、《真珠とり》などを立て続けに作曲したが、演奏されなかったり公演が芳しくなかったりなど、不遇の時代が続く。そんな中、師アレヴィが病気でこの世を去り、大きな後ろ盾のひとつを失ってしまった。だが、状況は好転する。彼の交響曲「ローマ」が初演され好評を博し、アレヴィの娘、ジュヌヴィエーヴと結婚した[3]。
19世紀パリの音楽と社会
ビゼーの生きた19世紀のフランスは、まさしく激動の時代であった。フランス革命以後の相次ぐ政変[4]、2度のパリ万博(1855・1867年)、ジョルジュ・オスマンによるパリの大改造など、人々の生活や価値観が一変したと思われる歴史的なトピックは枚挙に暇(いとま)がない。それは政体の変化もさることながら、公教育政策などを通じて「フランス」という国家が創り上げられていった時期でもある[5]。
この時代は、音楽というジャンルにおいても大きな変貌を遂げた時期であるといえる。アンシャン・レジーム期には王侯貴族の私的な消費物であった音楽は、名望家・ブルジョア(中産階級)の台頭によって主たる消費者が大衆化していくこととなる。音楽は見世物としての進化・深化を遂げ、サロンやコンサートホールではリストやショパンといったヴィルトゥオーゾ(名手)の園雄に熱狂的な観客が押し寄せた。またパリには次々とオペラ劇場が建設され、まさしく市民革命的熱気ともいうべきオペラ熱によって人々は(着飾って)劇場を訪れ観劇していった。この劇場の壮大な舞台装置を前提としてグランド・オペラと呼ばれるジャンルが確立する。こうした劇場に通うことが、(貴族ではない)上流階級の最大の箔のひとつであったといえる[6]。音楽家にとっては、一大マーケットであるパリで成果を挙げることが求められ、オペラでの成功が音楽家としての成功であったといえる。
《カルメン》の初演
音楽学者D・C・パーカーによれば、1872年の時点でビゼーは弟子のガラベールに手紙を書き「コミック座のために3幕仕立てのオペラを書くように頼まれている。メイヤックとアレヴィが台本を起こすだろう」と記している[7]。オペラ座を目指す若き作曲家にとって、足掛かりの仕事として重要視していたことが窺い知れる。
魔性の女カルメンは、文人メリメ(Prosper Mérimée)の短編小説(1845年)の主人公である[8]。1875年3月3日に初演された[9]。この作品は台詞入りのオペラ・コミック様式の一作であるが、初演に際し劇場側は、その台詞の生々しさに対する客席の拒否反応を恐れ、得意客をできる限り締め出した。その代わり、批評家・作曲家(グノー、トマ、ドリーブ、マスネ、オッフェンバック)、それにドーデやデュマ=フィスなど文壇の名士、シューダンスやアルトマンといった楽譜出版業者が劇場に集った。しかし、概ね良好だった客の反応は第1幕と第2幕のみで、第3幕ではミカエラのアリアだけに拍手が送られ、第4幕では氷河のごとき冷たさが場内を包んだという。
ビゼーの落胆は相当なものであったようだが、《カルメン》の評判は日増しに高まっていった[10]。これは、チャイコフスキーやサン=サーンスがその革新性を認め賞賛したためである。しかし、初演から3ヶ月後、36歳の若さでビゼーは亡くなっている。その死は、体調不良を訴えながらも冷たいセーヌ川で泳ぐという向こう見ずな行動がもたらしたとされ、喉の炎症をこじらせた彼は、1875年6月3日帰らぬ人となった。葬儀には同月5日にモンマルトルのラ・トリニテ教会で行われ、4,000人もの参列者があったという。遺骸はペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。これほどまでに早熟の天才が、37年に満たない短い生涯を閉じざるを得なかったことについて痛惜(つうせき)の念を禁じ得ないのは、筆者だけではなかろう。
あらすじ
ここで、《カルメン》のあらすじを紹介したい。
第1幕:
セビリアの街を警備する伍長モラレスの前で、同じ伍長のドン・ホセを探しにやってきたミカエラが兵士にからかわれる。警備の陣営が交代し、ホセが役目を引き継ぐ。煙草工場から女工たちが休憩で出てくる。カルメンはホセに目を留めつつ、〈ハバネラ〉を歌う。彼女が投げつけた花を拾い上げるホセの前に、ミカエラが姿を現す。ホセは母親の頼りを耳にする。女工同士の喧嘩でカルメンを捕まえるが、自分を見張るホセの彼女は〈セギディーリャ〉を歌って誘惑する。隊長のスニガがホセに護送を命じるものの、彼を籠絡済みのカルメンはまんまと逃げてしまう。
第2幕:
リリャス・パスティアの居酒屋にて。フラキータやメルセデスと一緒に、カルメンが〈ジプシーの唄〉を歌う。花形闘牛士のエスカミーリョが現れ、〈闘牛士の唄〉を披露し、カルメンに声を掛ける。ならずもののダンカイロとレメンダードが女たちに密輸の話を持ちかける。やってきたホセをカルメンが唄でもてなす。帰営を告げるラッパの音にホセは腰を浮かすが、怒るカルメンに彼は心からの愛情を口にする(二重唱〈花の歌〉)。カルメンはホセを自分たちの仲間に引き込もうと歌い出す。スニガが現れてホセと争いになるが、ジプシーの仲間がスニガを銃で脅して連れ出す。陣営の帰ることもできないホセは、密輸の仲間に入らざるを得なくなる。
第3幕:
山の中。荷物の担ぎ手が次々と現れ、火を焚いて休む。女たちがカルタ占いを始め、カルメンはカードに資の予言を読み取り、愕然とする。ミカエラが姿を現し、ホセを連れ帰る決意のもと、神に祈る。見張り役のホセが銃を撃つので彼女は岩に隠れる。入れ違いにエスカミーリョが登場、ホセと言葉を交わすうち、互いに恋敵と気付く。ホセが決闘を言い募り、2人は短刀でやりあうが、カルメンがエスカミーリョを救うために割って入る。エスカミーリョは皆を闘牛場に招待してからその場を去る。その後の引っ張り出されたミカエラが、母親の病をホセに告げる。彼は後ろ髪を引かれる思いで下山する。
第4幕:
セビリア。闘牛士たちが闘牛場に入り、カルメンとエスカミーリョは愛の言葉を交わす。フラキータとメルセデスが、ホセの姿が見える、注意しろとカルメンに忠告する。独り残った彼女の前に当のホセが現れ、やり直そうと縋(すが)る。カルメンはそれを拒み、彼から貰った指輪を投げ捨てる。激昂したホセは彼女を刺し、その屍にくずおれる。
ホフマン編
本演奏会では、フリッツ・ホフマン編曲版による組曲を演奏する[11]。この編曲版はオペラ本編とは異なり以下の構成となる。
第1組曲
第1曲:前奏曲(Prélude)(第1幕への前奏曲)〜アラゴネーズ(第4幕への間奏曲)このオペラの悲惨な結末を暗示する「運命の動機(Le Destin)」から始まり、続いて4幕で演奏されるアラゴネーズへと繋がる。打楽器によって3拍子のリズムが刻まれ、スペインのアラゴン地方からとった旋律がオーボエによって奏される。
第2曲:間奏曲(第3幕への間奏曲)元来《アルルの女》のために書かれた曲で、《カルメン》に転用された。ハープの分散和音に乗ったフルートの旋律が大変美しい。
第3曲:セギディーリャ(セグディーユ)スペイン・アンダルシア地方の大衆的なダンスをモチーフとした曲で、カルメンがドン・ホセを誘惑する場面で歌われる。
第4曲:アルカラの竜騎兵(第2幕への間奏曲)第2幕でドン・ホセが歌う旋律を用いており、ファゴットによる旋律が聴きどころである。
第5曲:闘牛士(第1幕への前奏曲)《カルメン》といえばこの曲を思い浮かべる方も多いのではないだろうか。第4幕の闘牛士の行進の旋律を使っており、躍動感あふれるテンポが特徴的である。
第2組曲
第1曲:密輸人者達の行進 第3幕の冒頭で演奏される曲で、フルートによって行進曲風の不気味な旋律が奏でられる。
第2曲:ハバネラ 第1幕でカルメンが歌う有名なアリアで、スペイン風の情緒豊かな旋律が魅力的である。
第3曲:夜想曲(ミカエラのアリア)第3幕でミカエラが歌う曲で、ホルンの牧歌的な前奏のあと、叙情豊かなヴァイオリンソロが奏される。
第4曲:闘牛士の歌 第2幕でエスカミーリョが登場する際に歌われ、編曲版ではトランペットのソロを堪能できよう。
第5曲:衛兵の交代(子ども達の合唱)第1幕で衛兵の交代の際、衛兵の列についてきた子供たちの合唱するユーモラスな行進曲である。
第6曲:ジプシーの踊り リリャス・パスティアの居酒屋で、フラスキータ、メルセデス、カルメンの3人で歌い踊られる時の音楽で、全幕を通じてもっともスペイン的といえる熱狂的な曲である。
註
[1] 初演されたのは1935年で、夫人のジュヌヴィエーヌに遺品を託された作曲家のアーンが19933年にパリ音楽院に寄付し図書館に所蔵されていた。長崎大学管弦楽団では、2005年6月5日のサマーコンサート2005において福田隆指揮で演奏している。
[2] 奨学金1,200フランは、ルコック(Charlres Lecocq)と並んでの首位だったため、等分している。
[3] 結婚についての紆余曲折は、ひのまどか『ビゼー―劇場に命をかけた男 (作曲家の物語シリーズ)−』(リブリオ出版、2007年)、98-108頁に詳しい。
[4] 名を付されている政体だけでも、第一共和制・第一帝政・第一復古(ブルボン)王政・ナポレオン百日天下・第二王政復古・七月王政(ブルボン=オルレアン朝)・第二共和制・第二帝政・第三共和制と移り変わる。福井憲彦編『フランス史(世界各国史12)』(山川出版社、2001年)
[5] 様々な「フランス」的なものをシンボルとして据えることで、複数の少数集団から「フランス」という国民国家を形成していった時期であるといえる。パリ近郊以外の地域ではとくに地方語(いわゆるフランス語以外の言語)による区分があり、レジオン・コミューンといった集団をも内包するかたちで統合が進められていった。重層的アイデンティティについての詳しい解説は、谷川穣・渡辺和行編著『近代フランスの歴史』(ミネルヴァ書房、2006年)を参照されたい。
[6] 家庭内にピアノを置き、子女を習わせることもステイタス・シンボルのひとつとして機能していたと言われている。
[7] Douglas Charles Parker, Georges Bizet His Life and Works (London: KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO., LTD, 1926), pp. 124-175.
[8] 本邦でも翻訳は多数出版されているが、プロスペール・メリメ(工藤庸子訳)『カルメン』(新書館、1997年)が代表的である。
[9] 初演に際しカルメンのキャスティングは難航したが、カルメンはセレスティーヌ・ガリ=マリエ(Célestine Galli-Marieé)ドン・ホセはポール・レリ(Paul Lhérie)エスカミーリョはジャック・ブーイ(Jacques Bouhy)、ミカエラ役はマルグリート・ショピ(Marguerite Chopis)が創唱した。Hervé Lacombe, Georges Bizet (Paris: Fayard, 2000).
[10] 公演は連続35回を記録し『ル・フィガロ』紙でも絶賛され、初演からすぐにウィーン帝室歌劇場から上演の申し入れがあったという。
参考文献
浅井香織『音楽の〈現代〉が始まったとき—第二帝政下の音楽家たち—』(中央公論社、1989年)
岡田暁生『オペラの運命—19世紀を魅了した「一夜の夢」—』(中央公論新社、2001年)
ジークフリート・クラカウアー(平井正訳)『ジャック・オッフェンバックと同時代のパリ』(せりか書房、1978年;筑摩書房、1995年)[Siegfried Kracauer, Pariser Leben, Jacques Offenbach und seine Zeit, Eine Gesellschaftsbiographie (Paul List Verlag München, 1962).]
ミシェル・カルドース(平島正郎・井上さつき訳)『ビゼー―「カルメン」とその時代』(音楽之友社、1989年)
プロスペール・メリメ(工藤庸子訳)『カルメン』(新書館、1997年)
谷川穣・渡辺和行編著『近代フランスの歴史−国民国家形成の彼方に−』(ミネルヴァ書房、2006年)
ひのまどか『ビゼー―劇場に命をかけた男 (作曲家の物語シリーズ)−』(リブリオ出版、2007年)
福井憲彦編『フランス史(世界各国史12)』(山川出版社、2001年)
Hervé Lacombe, Georges Bizet (Paris: Fayard, 2000).
Douglas Charles Parker, Georges Bizet His Life and Works (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd, 1926).